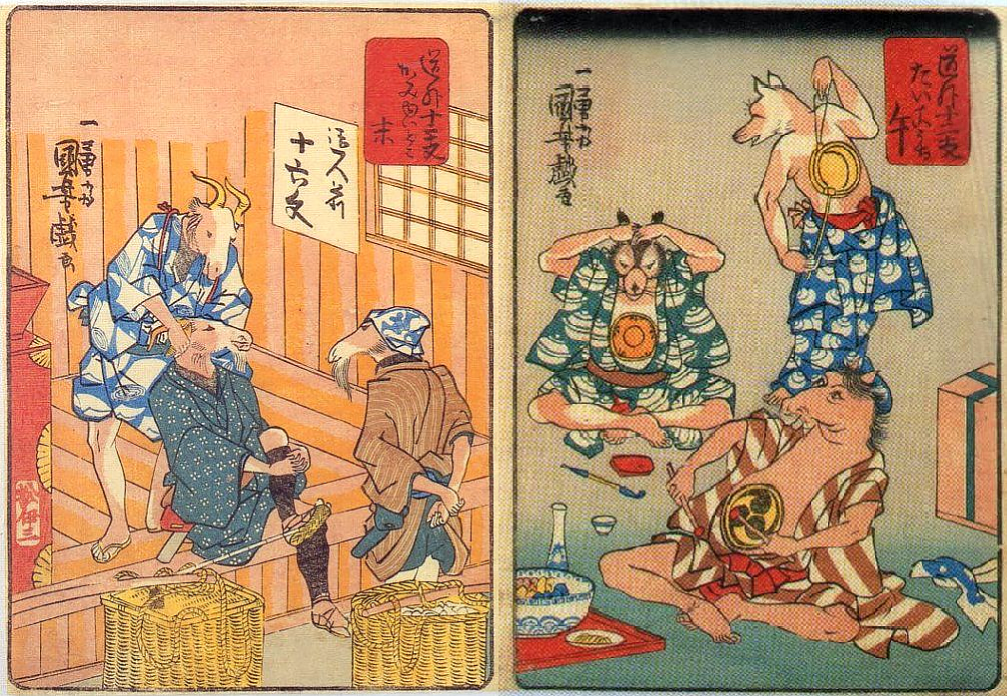保永堂版 東海道五十三次之内の序文
浮世絵を続き絵として刊行して完結後、組にして販売する時に目録と序文を付けることがあります。個々の絵を見ることはあっても、なかなか序文には出会えませんので、ここに、保永堂版東海道五十三次の序文をご紹介します。改行は原文のままです。
空かそふ大江戸のまちの真中にう
ちわたして我大御国の名をおほせ
たる橋のもとより内日刺都にのほる
東の海つ路五十ち余り三つのうまや
ちは年ことの春の始に子等かもて
遊ひくさにすなる道中すく六と
いふものにかの橋より宿々の絵かきて
ゆくみちのほとをもはかりしるしたるは
世の人のよくしれる所也しかはあれとそは
たゝ時の間のたはれ物にしあれは猶委
しうせむとて絵師広重ぬし其宿々は
さらなり名高う聞えたる家ゐあるは
海山野川草木旅ゆく人のさまなと
何くれと残る隈なく写しとられたるか
まのあたりそこに行たらむこゝちせ
られてあかぬ所なけれは後の世にも
伝へまくいそしみてこたひ竹内のあるし
板にゑられたるはしつかたに白き帋の
一ひらあなれはおのれに其ゆゑよしかい
つけてよとこはるゝまにまにつかみし
かき筆とりていさゝかをこなるたふれ
ことかきしるすにこそ
天保五とせに 俳諧歌房
あたるむつき 四方瀧水
空数ふ大江戸の町の真中に打ち渡して、我が大御国の名を負ほせたる橋の元より、うちひさす都に上る東の海つ路五十(いそぢ)余り三つの駅路(うまやぢ)は、年ごとの春の始めに、子等が持て遊びぐさにすなる道中双六といふものに、かの橋より宿々の絵描きて、行く道のほどをもはかり記したるは、世の人のよく知れる所なり。しかはあれど、そはただ時の時の間の戯(たは)れ物にしあれば、猶委(くは)しうせむとて、絵師広重ぬしその宿々はさらなり、名高う聞えたる家居、あるは海山野川草木、旅行く人のさまなど何くれと、残る隈なく写しとられたるが、目の辺りそこに行きたらむ心地せられて、飽かぬ所なければ、後の世にも伝へまく勤しみて、此(こ)度(たび)竹内(たけのうち)の主(あるじ)、板に彫(ゑ)られたる端つかたに白き帋(かみ)の一枚(ひとひら)あなれば、己に(おのれ)その故由(ゆゑよし)書い付けてよと、乞はるるまにまに柄(つか)短き筆執りて、いささか烏滸(をこ)なる戯(たふ)れごと書き記すにこそ
天保五年に当たる睦月
俳諧歌房 四方瀧水(よものたきすい)
〈要旨〉江戸の日本橋から京までの五十三の宿駅については、毎年正月に子供達が遊ぶ道中双六に描かれているが、このたび広重師がそれをさらに詳しく、住居景色、旅人の様子まで描き尽くしたので、まるでその場所に行くような気持ちにもなり、これを後世に伝えたいと思ったところ、竹内孫八氏がこれを板行し、その余白にこのいきさつを書くようにと私に命じたので、至らぬ筆でこのようにに書いたものです。
天保五年(1834)正月 四方滝水
四方滝水(よものたきすい) 江戸後期の狂歌師。通称は榎本治兵衛、のち三右衛門、別号を狂歌房・吾友軒。晩年、四方滝水・滝水楼と改めた。大田蜀山人門下。版本挿絵や狂歌摺物などを手がけた後、晩年は本絵師として肉筆の美人風俗画を描く。和文にも巧みで、蜀山人主催の「和文の会」の一員となった。その著『観難誌』は天明・寛政期の狂歌界を知る貴重な資料である。生没年不詳。(WEBの美術人名辞典・思文閣)
滝水は江戸時代の酒の名で、義士銘々伝のうち「赤垣源蔵徳利の別れ」に、赤垣源蔵が兄に別れを告げに来た時に、兄と酌み交わそうと下げて来た酒が滝水二升で、「うまい、酒は滝水にとどめ刺す」と言っています。